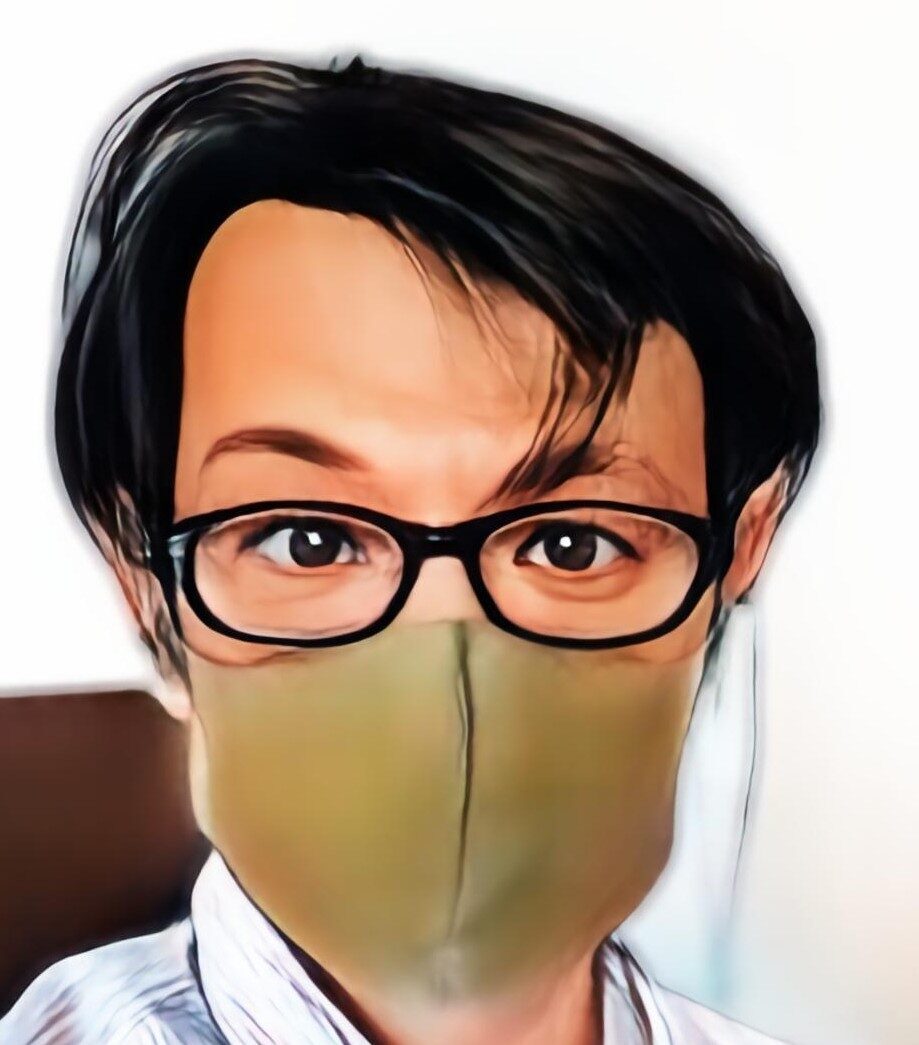最初の目標は「車椅子の自走」

リハビリ病院に来てから2週間ほどで、体調の良い日はリハビリルームでの訓練がメインになりました。最初の目標は、看護師や療法士の助けを借りずに自力で車椅子を動かして移動することでした。
片麻痺患者にとっての車椅子の難点
片麻痺患者にとって、車椅子の操作には両手が使える方とは異なる困難が伴います。一般的に、手動車椅子は両腕を使って車輪をこぎ、自走・方向転換・停止といった動作を行います。しかし、片麻痺の場合、片方の腕が思うように動かせないため、車椅子をバランスよく操るのは容易ではありません。
右手と右足を使った独特な操作方法
私は左半身に麻痺があるため、主に右手と右足を使って操作することになります。左手で左側の車輪をこぎながら、左足で地面を蹴って進むという動きは、言葉で書くよりずっと複雑で、常に体のバランスと進行方向を意識しなければなりません。とくに方向転換が難しく、右に曲がりたいときなどは麻痺側の車輪に力が加えられないため、車椅子が斜めに傾いたり、変な角度で止まってしまうことがよくありました。
片麻痺の車椅子生活は困難
さらに、室内の狭いスペースや人通りの多い場所では微調整が必要で、そのたびに何度も動きを止めては向きを修正しなければならず、体力だけでなく集中力も奪われていきます。段差やスロープの角度が少しあるだけでも車椅子が傾きやすく、危険を感じる場面も少なくありませんでした。
片麻痺の体での車椅子操作は、ただ「乗る」だけではなく、「自分の体に合わせて、乗りこなす」ための工夫と努力が必要だと痛感しています。こうした経験を通して、日々の移動がどれほど高度な行動か、そして自立に向けてどれだけの試行錯誤が必要かを実感しました。
障壁だった「扉」と「段差」
入院生活では、思いがけない障壁も多数存在しました。特に大変だったのが扉の開閉です。
- 引き戸:比較的開けやすい
- 開き戸:ドアノブを握って車椅子ごと押し引きするのは一苦労
健常な頃には意識しなかった「段差」や「傾斜」も、今では大きな壁に感じました。
車椅子生活を通じて得た“気づき”

車椅子の生活は、単なる「移動手段の変化」ではなかった。視線の高さが変わることで、見える世界も変わった。以前は気にも留めなかった段差や傾斜が、今では「障壁」に見える。一方で、誰かが無言でドアを押さえてくれる、その優しさが心に深く残るようになった。日常のひとつひとつに、人の思いやりが染み込んでいることに、ようやく気づけた。
- バリアフリーの重要性
- 人の手を借りるありがたさ
- 一歩一歩の進歩の喜び
また、できなくなったことに目を向けるよりも、「今できること」に意識を向ける大切さも学んだ。工夫すればできることが増える。それは決して「諦め」ではなく、「挑戦の形」なのだと知った。家族の支えや、周囲の言葉に励まされながら、自分自身の心の持ちようも変わっていった。
車椅子生活は不自由の連続だったが、その中にこそ、当たり前だった日常の尊さと、感謝の気持ちが芽生えた。気づきを重ねるたびに、自分という人間の輪郭が、少しずつ強く、優しくなっていくのを感じている。
今後の目標|いよいよ歩行訓練が始まる!

今では、車椅子での自力移動もすっかり慣れ、病院内の移動はほとんど問題なく行えるようになりました。リハビリルームへは毎日決まった時間に一人で通い、食堂では自分でトレーを取りに行き、食事も落ち着いてとれるようになりました。トイレにも介助を必要とせず、一人で安全に出入りできるようになったのは、大きな進歩です。
振り返れば、片手片足での操作に苦労していた日々が嘘のようです。身体だけでなく、気持ちにも少しずつ自信が戻ってきました。そして今、いよいよ次のステージ――歩行訓練が始まろうとしています。まだ不安はありますが、自分の足で一歩を踏み出すための準備はできています。ここまで来られたことに感謝しながら、次の挑戦に向かおうとしています。