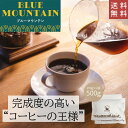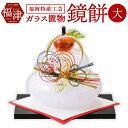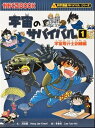1月9日はブルーマウンテンコーヒーの日です

1月9日は、ジャマイカコーヒー輸入協議会が制定した「ジャマイカコーヒーの日」です。この記念日は、輸入ジャマイカコーヒーの品質維持向上や秩序ある流通を目的としています。
特に注目すべきは、1967年1月9日にジャマイカ産コーヒーが首都キングストンの港から日本向けに初めて大型出荷されたことです。この際、1400袋(1袋60Kg相当)のコーヒーが日本に届けられました。これを機に、日本とジャマイカのコーヒー文化の交流が深まり、現在でもブルーマウンテンコーヒーなどの高品質なジャマイカコーヒーが多くのコーヒーファンに愛されています。
ジャマイカコーヒー

ジャマイカコーヒーは、繊細な味で香りが高いのが特徴で、他の香りが弱いコーヒー豆とブレンドされることが多い品種です。また、味わいは際だつ甘味と調和の取れた酸味が特徴といわれています。このジャマイカコーヒーは、コーヒーの王様と呼ばれていて、現在では麻袋ではなく樽詰めで輸出されているようです。
ブルーマウンテンと樽

ブルーマウンテンは、唯一コーヒーの中で樽詰めで輸出されています。18世紀中頃からイギリスの植民地時代、イギリスからの小麦粉などに使用して空いた樽をリサイクルし、ラム酒やコーヒーなどを入れて出荷したのが始まりだといわれています。また、ブルーマウンテンに使われる樽の材質は、アメリカの温帯林の物であるため、匂いがないそうです。そして、木が湿気を吸収し放出するため内部の変化を与えません。その上、輸送時に起こる急激な温度の変化を緩和することができます。こういうメリットがあるために樽に詰めて輸出されるのです。
ブルーマウンテンの栽培される産地

ジャマイカの80%が山地であり、その最高峰「ブルーマウンテン」で標高が2256mある山です。この地は、全体的に亜熱帯海洋性気候で日光と雨や濃霧があって、昼と夜の温度差が激しいのが特徴です。実際にコーヒーを栽培するにあたり、土壌や日中寒暖差と雨量、栽培高度が良質のコーヒーにとって良い条件が整っています。
香りと後味の良さは、No.1!?

コーヒーは、最低3人の国家資格を持つ検査官の品質検査により、6項目の味覚鑑定が行われます。そして、その検査に合格したものだけが認められます。その検査でNo.1の称号が得られるのは3割程度だそうです。その6項目の味覚鑑定内容は、「香り」「酸味」「炒りあがり」「コク」「後味」「雑実・異味」です。
そこで、私個人が興味深いのは香りと後味です。美味しいコーヒー店に行くとその香りにつられて入店してしまい、後味でまた来ようとリピーターとなります。美味しいコーヒーがきっかけで人気店になるのも分かるような気がします。