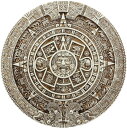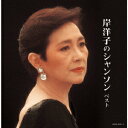「ハボタン」

基本情報
- 分類:アブラナ科アブラナ属(ケールの園芸品種)
- 学名:Brassica oleracea var. acephala
- 原産:ヨーロッパ
- 形態:多年草(日本では一年草として扱われることが多い)
- 開花期:春(ただし観賞されるのは“葉”の色)
- 別名:葉ボタン、観賞用キャベツ
- 用途:冬の花壇・寄せ植え・正月飾りとして人気
ハボタンについて

特徴
- 花ではなく葉が色づく
赤・白・ピンク・紫など、中心部の葉が鮮やかに発色する。
- 寒さで色が深まる
低温に当たるほど発色が良くなり、冬にもっとも美しくなる。
- 形のバリエーションが豊富
・丸く重なり合う“丸葉”
・フリルのような“ちりめん系”
・細長い“切れ葉系” など。
- 丈夫で育てやすい
耐寒性が高く、冬のガーデニングに重宝される。
- 長期間観賞できる
花壇に植えると、真冬でも色を保ち続け、春先まで楽しめる。
花言葉:「祝福」

由来
- お正月飾りとして使われてきた歴史
昔から、ハボタンは「縁起物」として正月の寄せ植えや迎春アレンジに用いられ、新年を迎える“祝いの装い”として親しまれてきた。
- 牡丹(富貴・華やかさの象徴)を思わせる姿
その名の通り牡丹のように重なり合う華やかな葉姿が、“門出を寿ぐ花”というイメージと結びついた。
- 冬の寒さのなかでも鮮やかに彩る力強さ
暗い季節に彩りを添えることが「幸福を呼び込む」「未来を明るくする」という象徴になった。
これらの背景が合わさり、**「祝福」「物事の門出を祝う」**という花言葉へとつながったとされる。
「冬の庭に、ひそやかな祝福を」

雪の気配をふくんだ風が、庭の木々を震わせていた。師走の午後、陽はもう傾きかけている。凪沙は手袋の指先をこすり合わせながら、花壇にしゃがみ込んだ。そこには、赤や白、紫に色づいたハボタンが静かに並んでいる。
「……今年も、変わらずきれい」
ひとつ、そっと触れる。葉なのに花のように重なり合う姿は、まるで冬の牡丹だといつも思う。小さなころ、祖母がよく話してくれた。
――ハボタンはね、寒い季節でも、ちゃんと色を深めて咲くんだよ。
――だから、お正月の庭には欠かせないの。家に福を呼ぶんだって。
その声を思い出すたび、胸に暖かいものが広がる。
今年の冬は特に冷え込む。家の中にいる時間が増え、祖母がいなくなって初めて迎える正月の準備は、どこか心細かった。庭も、少し寂しく見えた。だからこそ、せめて祖母が毎年植えていたハボタンだけは、同じ場所に並べようと決めたのだ。
植え付けを終えたとき、背後で落ち葉を踏む音がした。
「お手伝いしようか?」
振り返ると、隣に住む蒼介が立っていた。幼馴染で、祖母とも親しくしてくれていた青年だ。温かい湯気の立つマグカップを二つ持っている。
「わ、ありがとう。……なにそれ?」
「生姜紅茶。冷えてるだろうと思って」
ふたりで縁側に腰をおろし、湯気をふうと吹きかけながら庭を眺めた。冬の光を受けたハボタンの中心が、ほんのりと輝いて見える。
「凪沙のおばあさん、よく言ってたよな。ハボタンは“祝福の花”だって」
蒼介の言葉に、凪沙は小さくうなずいた。
「うん。冬の庭が寂しくならないようにって、毎年植えてた。お正月の寄せ植えにも、必ず入れてたんだよ。縁起がいいからって」
「たしかに、冬の庭であんなに色づいてるのって、不思議なくらい力強いよな」
蒼介の視線が、そっと花壇に向けられる。
「祖母がね、言ってたの。寒くても色を深めて、美しく残り続けるから“未来が明るくなる”って。門出を祝ってくれるんだって」
そう言うと、胸の奥で、祖母の笑い声がふっとよみがえった気がした。
しんとした夕暮れの空気の中で、ハボタンは風に揺れながら静かに光っている。その姿を眺めていると、どこかで見守られているような、不思議な安心感があった。
「……凪沙」
蒼介が少し迷ったように、言葉を続けた。
「今年さ、仕事で色々あって、落ち込んでる時期があったんだ。けど、ここを通るたびに思い出したんだよ。君のおばあさんが言ってた“祝福”の話。冬でも色を失わないハボタンを見ると、なんか……また頑張れる気がして」
凪沙は、驚いて彼の顔を見た。
「そんなふうに思ってくれてたんだ」
「うん。だから……来年も、この花、いっしょに植えられたらいいなって。もし、よかったらだけど」
頬がすこし熱くなる。ハボタンが、夕陽のなかで微笑んだように見えた。
「うん。来年も、その次の年も。いっしょに植えよう」
言葉にした瞬間、風がふっと吹き、色づいた葉が柔らかく揺れた。まるで祝福の拍手のように。
冬の庭は静かだけれど、その奥には確かな温もりがあった。凪沙はそっと目を閉じ、祖母に届くように小さく呟く。
「おばあちゃん、今年もちゃんと植えたよ。……ありがとう」
その声に呼応するように、夕暮れの光がハボタンを優しく照らした。
寒さのただなかで色を深める花。その姿は、未来へ向かう小さな“門出”を、ひそやかに祝福しているようだった。