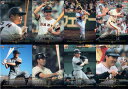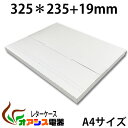「ダチュラ」

基本情報
- 分類:ナス科ダチュラ属(一年草,短命な多年草)
- 学名:Datura metelなど
- 原産地:インド、中東、南北アメリカ
- 和名:チョウセンアサガオ(朝鮮朝顔)
- 草丈:1〜2mほどに育つ
- 花期:夏〜秋
- 花色:白、紫、黄色など
- 特徴:大きなラッパ状の花を咲かせ、甘く強い香りを放つ。夜に咲く種類が多く、幻想的な雰囲気を持つ。
ダチュラについて

特徴
- 花姿
ラッパ型の大輪の花はエキゾチックで華やか。夜に咲き、月明かりに照らされる姿は神秘的で美しい。 - 香り
芳香が強く、遠くからでも気づくほど。ただしその魅力的な香りの裏には強い毒性が潜む。 - 毒性
アトロピン、スコポラミンなどのアルカロイドを含み、少量でも中毒を起こす。昔は魔女の薬や幻覚剤として用いられた伝承も残る。
花言葉:「偽りの魅力」

由来
ダチュラに「偽りの魅力」という花言葉が与えられた背景には以下のような理由があるとされています。
- 美と毒のギャップ
見た目は華やかで、香りも甘美だが、内実は猛毒を秘めている。その「人を惹きつけながらも命を脅かす性質」が「魅力的に見えても危険=偽りの魅力」と解釈された。 - 幻惑のイメージ
摂取すると幻覚や陶酔感を引き起こすため、現実を歪ませる「偽りの世界」を見せる花として捉えられた。 - 夜に咲く妖しい美しさ
夜の闇に浮かぶ白い花姿は神秘的で人を魅了するが、それは一時的であり、危険と隣り合わせの「まやかしの美」と考えられた。
「偽りの魅力」

古い屋敷の庭の奥、誰も近づかぬ石垣のそばに、その花は咲いていた。
夜になると、大きな白い花が闇に浮かび上がり、甘い香りを辺りに漂わせる。その香りは人を誘うように濃厚で、風に乗って屋敷の奥まで忍び込む。
――ダチュラ。
村の人々はその名を口にするのを嫌い、ただ「魔女の花」と呼んで恐れていた。
屋敷に住む青年・廉は、その花に心を奪われていた。
昼間は何の変哲もない緑の茂みにしか見えないのに、夜になると突如として現れる純白の花。その姿は清らかで、どこか人ならぬものの気配をまとっている。廉は気づけば毎夜、花の前に立ち尽くしていた。

ある夜、香りがひときわ強く漂った。気づけば視界が揺らぎ、花がまるで人の姿をとったかのように見えた。
「いらっしゃい、ずっと待っていたの」
白い衣をまとった女が、そこに立っていた。透き通るような肌、夜の闇に溶ける黒髪。廉は抗うこともできず、その幻影に手を伸ばす。
女は微笑み、彼の耳元に囁いた。
「わたしと一緒に来て」
気がついたとき、廉は屋敷の床に倒れていた。額には冷や汗がにじみ、呼吸は乱れ、喉が焼けつくように乾いていた。夢だったのか――そう思いたかったが、唇にはまだ甘い香りが残っている。

その晩から、廉は花の幻影に取り憑かれるようになった。食事の味は感じられず、眠っても女の声が耳元で響く。「もっと近くに」「わたしを抱きしめて」。やがて彼は衰弱し、鏡に映る自分の顔が日に日に痩せ細っていくのをただ見つめるしかなかった。
村の老婆がその噂を聞きつけ、屋敷を訪ねてきた。
「おまえ、あの花に魅入られたのだね」
老婆の目は鋭く、廉はうなずくしかなかった。
「ダチュラは人を惑わす。姿も香りも美しいが、その実は毒そのもの。ほんのひと嗅ぎでも心を奪い、偽りの夢へと引きずり込む。命を削られても気づかぬまま……」

老婆は庭へ向かい、花に塩を撒き、呪文のような言葉を唱えた。白い花は震え、やがて力尽きたように萎れた。
その瞬間、廉の胸の重さがすっと消え、あの甘い幻影も霧散していった。
それからというもの、廉は二度と花の咲く夜の庭へ近づかなかった。
しかし、月の明るい晩になると、ふと耳の奥に声がよみがえる。
「あなたは、また来てくれるでしょう?」
彼は恐怖に身を震わせながらも、その声の甘美さを忘れることができなかった。
――美しさの裏に潜む毒。それが「偽りの魅力」なのだと、廉は身をもって知ったのである。