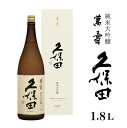「ホワイトレースフラワー」

基本情報
- 学名:Ammi majus
- 科名:セリ科
- 原産地:地中海沿岸地方~西アジア
- 和名:ドクゼリモドキ(毒性のあるセリに似ていることから)
- 開花期:5月~6月(切り花はほぼ周年)
- 花色:白
- 草丈:60~100cm程度
花束やアレンジメントに添えられることが多く、「レースフラワー」の名で親しまれています。
ホワイトレースフラワーについて

特徴
- 小花が傘のように広がる
無数の小さな白花が集まって、まるでレース編みのような繊細な姿を作ります。 - 可憐で軽やかな雰囲気
主役の花を引き立てる「名脇役」として使われ、花束に清楚さや優雅さを添える存在です。 - ハーブとしての一面
原産地では古くから観賞用だけでなく、薬草的にも扱われてきました。 - 似ている花との違い
ニンジンの花やレース状に咲く「オルラヤ(オルレア)」とよく似ていますが、ホワイトレースフラワーはより繊細で花の数が多い傾向があります。
花言葉:「可憐な花」

由来
「可憐な心」という花言葉は、花の姿そのものに由来しています。
- 繊細な小花の集まり
ひとつひとつの花はごく小さく、主張せずに寄り添って咲きます。
→ その奥ゆかしく控えめな姿が、「可憐で純粋な心」を思わせる。 - レースのような美しさ
華美ではなく、柔らかで上品な美しさがあり、「可憐」という言葉が自然に重ねられた。 - 調和と支え合い
中心の花を引き立てるように周囲を囲む姿は、自己主張よりも「思いやりある心」を表現していると考えられた。
「可憐な心」

放課後の教室には、もうほとんど人が残っていなかった。窓から差し込む夕陽が、机の上に置かれた小さな花瓶を淡く照らしている。そこには、真っ白なホワイトレースフラワーが一輪だけ挿されていた。
「これ……誰が置いていったんだろう」
涼子は首をかしげた。花瓶は図工室から持ち出したものだろうか。差してある花は、校庭に咲いているものではない。花屋で買ったのか、あるいは家の庭から摘んできたのか。

彼女はそっと花に顔を近づけた。小さな花が無数に集まって、ひとつの大きな傘のような形を作っている。主役になろうとする花ではなく、控えめに、けれど確かな存在感でそこにある。
「……なんだか、綺麗」
思わずそう口にすると、背後から声がした。
「気づいた?」
振り返ると、同じクラスの健太が立っていた。いつもは冗談ばかり言う彼が、珍しく真剣な顔をしている。
「これ、君にあげたんだ」
「えっ、わたしに?」
涼子は驚いた。自分が花をもらうなんて、想像したこともなかった。

「花言葉、知ってる?」健太は少し照れたように笑った。「ホワイトレースフラワーには、『可憐な心』っていう意味があるんだ」
涼子は花を見つめ直した。確かに、一つ一つはとても小さくて、主張しすぎない。けれど集まることで、レースのように柔らかで美しい模様を描いている。
「……どうして、それを私に?」
健太は一瞬、言葉を探すように視線を泳がせた。やがて、小さな声で続けた。
「君ってさ、いつもみんなのこと気にしてるだろ。授業中でも、誰かが困ってたらすぐに助けてるし。大きな声で自分をアピールしたりはしないけど、ちゃんと周りを支えてる。そういうところ、花言葉みたいだなって思ったんだ」

涼子の胸が熱くなった。自分のことをそんなふうに見ていてくれる人がいるなんて、考えもしなかった。
窓の外では、夕焼けが少しずつ群青色に変わっていく。沈黙が落ちる中、涼子はそっとホワイトレースフラワーに触れた。
「ありがとう。……すごく、嬉しい」
彼女の言葉に、健太は安心したように笑った。その笑顔はどこかぎこちなかったけれど、誠実さがにじんでいた。
その瞬間、涼子の心に芽生えた感情は、まだ名前をつけられない。けれど、確かに暖かい光のように胸を満たしていた。
花瓶の中の白い小花たちは、夕暮れの光を受けてかすかに揺れた。まるで二人の心を見守るように、可憐で純粋な姿を輝かせながら。