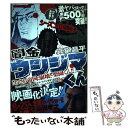「スパティフィラム」

基本情報
- 学名:Spathiphyllum
- 科属:サトイモ科・スパティフィラム属
- 原産地:熱帯アメリカ(コロンビア、ベネズエラなど)
- 英名:Peace Lily(ピースリリー)
- 開花期:5月~10月
- 形態:常緑多年草。観葉植物として室内で栽培されることが多い。
スパティフィラムについて

特徴
- 純白の仏炎苞(ぶつえんほう)
花のように見える白い部分は花びらではなく「仏炎苞」と呼ばれる苞葉。中心に立つ黄色や淡緑色の棒状の部分が本来の花序。 - 空気清浄効果
NASAの研究で「空気清浄植物」として知られる。ホルムアルデヒドやベンゼンなど有害物質を吸収する能力があるとされる。 - 育てやすさ
半日陰を好み、乾燥にもある程度強い。オフィスや家庭の観葉植物として人気。 - 姿の美しさ
艶のある濃緑色の葉と純白の仏炎苞のコントラストが美しく、清潔感を与える。
花言葉:「清らかな心」

由来
スパティフィラムの代表的な花言葉のひとつが 「清らかな心」 です。
この由来には次のような理由が考えられます。
- 白い仏炎苞のイメージ
真っ白な仏炎苞は、汚れのない純粋さを象徴し、見る人に「無垢」「清浄」を思わせる。 - 平和の象徴としての英名
英語名 Peace Lily(平和のユリ) は、白い旗=「停戦・平和の象徴」を連想させる。そこから「清らか」「穏やかな心」という意味につながった。 - 凛とした立ち姿
余分な装飾を持たず、清楚に立ち上がる姿は、内面の清らかさを花姿に映し出すものと考えられてきた。
「清らかな心」

祖母が亡くなったとき、私は遺影の横に一鉢のスパティフィラムを見つけた。
光沢を帯びた深緑の葉の間から、真っ白な仏炎苞がすっと立ち上がっている。喪服に包まれた人々の黒に囲まれて、それはまるで一点の汚れも許さぬように、凛とした気配を放っていた。
「おばあちゃん、この花、好きだったの?」と私が問いかけると、母は少し微笑んで頷いた。
「ええ。ほら、英語ではピースリリーって呼ばれてるでしょう? 平和の象徴みたいな花だって言って、よく眺めていたのよ」

私は知らなかった。祖母が花を愛でる姿は幾度となく思い出せるけれど、その名前や由来までは気に留めてこなかった。
葬儀の夜、私は眠れずにいた。居間に置かれたスパティフィラムの鉢のそばに腰を下ろすと、不思議なことに胸のざわめきが静まっていくのを感じた。
仏炎苞は白い旗のようだった。戦いを終える合図の旗。心の中で渦巻いていた後悔や言葉にならない感情が、少しずつほどけていくように思えた。
私は花に向かって話し始めた。
「ごめんね。おばあちゃんに、ちゃんとありがとうを言わなかった」
声に出した瞬間、涙が溢れた。だが、花は静かにそこに立ち、まるで「それでいい」と受け止めてくれているようだった。

祖母の残した言葉を、母が語ってくれたことがある。
――人の心は汚れやすいものよ。でもね、ほんの少しでも清らかであろうと願う気持ちがあれば、それで十分なの。
白い仏炎苞は、その言葉の具現のように見えた。余計な飾りもなく、ただ真っすぐに空へ伸びている。その姿は「清らかな心」という花言葉そのままだった。
葬儀が終わり、人々が去ったあと、私はスパティフィラムを自分の部屋へ持ち帰った。窓辺に置かれた鉢は、朝の光を浴びてまた新しい白を開いた。
その清らかさは、祖母が私に残してくれた最期の贈り物のように思えた。

以来、私はときどき花に向かって語りかける。
仕事で心が荒んだとき、誰かを傷つけてしまったとき。
その度に、白い花は静かに私を見つめ返し、「穏やかであれ」と諭してくれる。
清らかな心を持ち続けることは、難しい。けれど、この花の前に立つと、ほんの一瞬だけでも、心の奥に澄んだ水面が広がる気がする。
私はそれを大切にしようと思う。祖母がこの花に託した思いを、受け継ぐように。
窓の外では、風が街路樹を揺らしている。だがスパティフィラムは、動じることなく真っ白な苞を立ち上げていた。
――清らかな心。
それはきっと、嵐の中でも失われない、ささやかな灯のようなものなのだ。