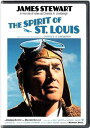「レモン」(檸檬)
基本情報
学名 :Citrus limon 分類 :ミカン科(Rutaceae)・ミカン属(Citrus)原産地 :アジア、ヨーロッパ、中近東、北アメリカ、アフリカの一部果実の特徴 :
楕円形で先端に小さな突起がある
黄色い果皮に酸味の強い果汁
ビタミンCが豊富で、風邪予防や美容に効果があるとされる
樹高 :通常2~6メートル花の色 :白(時に外側が薄紫がかる)開花時期 :5月中旬~6月上旬(主な開花期)、6月中旬~11月(品種によって適時、開花)
レモンについて
特徴
香り高い果実 :四季咲き性 :観賞価値も高い :
花言葉:「情熱」
レモンの花言葉にはいくつかありますが、「情熱 」という言葉は特にその強い香りと鮮烈な酸味に由来します。
由来の考察:
香りと味が刺激的で印象的なこと 花の清らかさと果実の力強さの対比 古代からの薬効や神話的イメージ
「レモンの情熱」
六月の風は、まだ夏の匂いを運んでこない。
「ほら、咲いたよ」
小さな五弁の花は、思い出よりもずっと繊細だった。
——あのとき、私は東京から逃げてきた。
「情熱っていうのよ、この花の花言葉」
「レモンが情熱? 似合わない」
「でもね、あの花がなかったら、あの果実はできないのよ。
祖母の言葉が、今ごろになって胸に刺さる。
「レモネード、飲む?」
一口飲むと、きりっとした酸味が舌を刺激する。
「これ、庭のやつ?」
果実は確かに情熱のかたちだ。
あの頃は知らなかった。
「情熱って、案外静かなのね」
従妹がきょとんとこちらを見る。
夕暮れ、レモンの木に残る最後の陽が差す。
私は一輪、咲きかけの花をそっと手折り、ポケットにしまう。