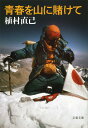7月22日はディスコの日です
1978年7月22日、ジョン・トラボルタ主演の映画「サタデー・ナイト・フィーバー」が、日本で初めて公開されました。そして、MCとミキシングの両方をこなすDISCO DJのスペシャリスト「DJオッシー」が、この魅力をより多くの人に知ってもらうことが目的で、この日を「ディスコの日」として制定しました。また、この「ディスコ」は、レコードで音楽を流してダンスを踊る空間として、1970年代から若者の人気を集めてきました。
ディスコの歴史

社交場としてのダンスホールは、実はかなり昔からあったそうです。しかし、第二次世界大戦中に生バンド演奏が困難になり、その状況に困ったナイトクラブがバンド演奏の代わりにレコードを流しました。それが、ディスコ形態の始まりとされています。
パリ、「ラ・ディスコティーク」

1942年3月、パリに「ラ・ディスコティーク」と呼ばれるナイトクラブが開店します。そして、第二次世界大戦後の1947年8月、やはりパリで「ウイスキー・ア・ゴーゴー」をオープンします。アメリカ人の「エルマー・ヴァレンタイン」は、フランス旅行中にこのナイトクラブを訪れ、刺激を受けました。
世界的なゴーゴーブームの原点がスタート!

そして、1964年1月にエルマーは、ロサンゼルス・サンセット大通りにアメリカ版「ウイスキー・ア・ゴーゴー」をオープンします。このことから、生バンド演奏と女性DJ、レコード演奏を併用したことが評判を呼び、世界的なゴーゴーブームの原点となります。当時のアメリカ・ニューヨークでも「ペパーミントラウンジ」などナイトクラブが存在していましたが、当時はライブ演奏とダンスホールが基本だったそうですが、1968年には「フランシス・グラッソ」が「DJによるナイトクラブ」を提案し、ニューヨークに「サルヴェイションⅡ」をオープンします。
ニューヨークで一気に広がり、ディスコの原型が完成

さらに、1969年になると「サンクチュアリ」をはじめ複数の店が続々とオープンし、70年代ディスコの基本形のようなものがを確立します。これらのお店はロフトを利用したり、教会を改装するなど今まであったナイトクラブのやり方にこだわらない空間だったそうです。またそこは、最新の流行音楽のレコードを流し、DJによる個性的なプレイやミキシングなども行っていたといいます。
ジェームス・ブラウンやクール&ザ・ギャングが登場!
その後は、ジェームス・ブラウンやクール&ザ・ギャングなどが人気を集め、初期ディスコ音楽の主流となります。そして、1970年代になるとニューヨークに「ニューヨークニューヨーク」や「スタジオ54」といった巨大ディスコがオープンします。その中でも1977年にオープンした「スタジオ54」はファッショナブルなセレブが集うニューヨークならではのナイトクラブとなっています。
40代~50代の客中心にディスコが復活!?

六本木ヴェルファーレの閉店後、日本のディスコの灯は一旦途絶えますが、2010年11月に「マハラジャ六本木」が復活。それをきっかけに、バブル期に青春を過ごした40代~50代の客が再び人気を集め、大阪や名古屋、祇園や仙台も続々と復活したそうです。さらにディスコの復活は、ホテル業界に刺激を与えて「グランドハイアット東京」で2005年末からイベントを実施しているようです。
私は、バブル崩壊後に大人として社会に出てきた人間です。やはり当時の日本は、敗戦のどん底から這い上がり、経済大国となると輝かしい実績を挙げ、誰もが誇らしげにしているように思えました。これも若者が、がむしゃらに仕事と向き合い、そのストレスをディスコなどで発散しながら突っ走った結果なのでしょう。