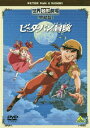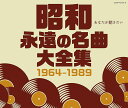12月28日は身体検査の日です

1888年12月28日は、日本の教育史において重要な日です。この日、文部省(現在の文部科学省)は全国の学校に対し、毎年4月に生徒の「活力検査」(現在の身体検査)を実施するよう訓令を出しました。これにより、学校における健康管理が体系的に行われるようになりました。
身体検査

「身体検査」は、身長・体重など身体的な発育状況や健康状態を記録するものです。この検査は、主に学校や企業などで行われていて、属に「健康診断」と呼ばれる場合もあります。検査対象は、身長や体重から視力や聴力など、その種類は色々とありますが、中には「座高」のように廃止されたものもあります。
座高の測定
「座高」の測定は、椅子に座って上体を測定器に当てて、姿勢を真っ直ぐにします。そして、座ったお尻の面から頭までの上体の高さを測定することです。
座高測定の意義は不明!?

元々座高の測定は、上半身発達の指標でしたが実際のところ、その測定の意義は不明確でした。1935年頃の日本は、内臓が発達していれば健康だとされて、そのことから座高が高ければそれだけ内臓が発達していると思われていたのです。
座高の測定は意味がない
この事から「測定に意味がない」とされ、検査結果も活用するところがない事からなどの理由で、2014年に学校保健安全法施行規則を改正しました。そして、2016年4月から規定の診断項目から除外されたということです。
新たに追加された検査もある

除外されたものある中で、追加されるものもあります。文科省では、学校の健康診断で「関節・筋肉・骨」などの異常を検査する新たなものを導入する方針だそうです。現在人は、運動不足でしゃがむことができない子供や、クラブ活動のやり過ぎによる炎症になる子供が増えていて、これらの健康課題を早期に発見するという目的です。
今時の子供は和式トイレが使えない!?
今どきの子供は、筋力不足で和式のトイレで用を足せないとか、跳び箱で手をついただけで骨折するケースもあると聞きます。そういった事から測定項目が変化していくのは、異常を早期発見し、改善することができるので、たいへん良いことだと思います。