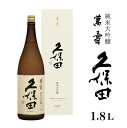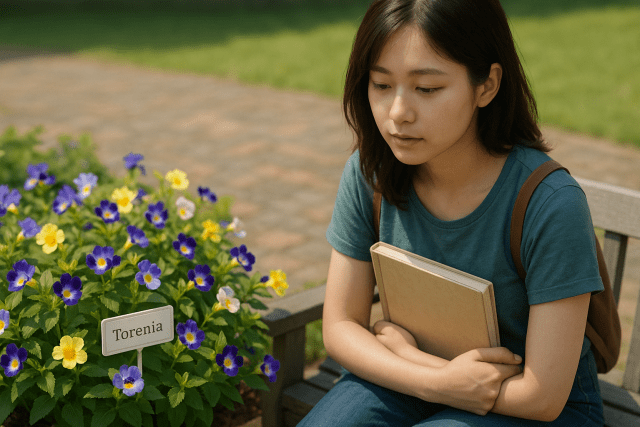10月2日はスヌーピーの日です

1950年のこの日は、チャールズ・モンロー・シュルツ作の漫画「ピーナッツ」がアメリカの新聞で掲載を開始した日です。スヌーピーという名前がこの「ピーナッツ」を指す代名詞となっています。また、名前のスヌーピーは「うろうろ嗅ぎ回る」などを意味で「snoop」からきたそうです。
- チャールズ・M・シュルツ
- シュルツの生涯
- スヌーピーが登場する「ピーナッツ」
- タイトル『L’il Folks』、予定!?
- 個性豊かなキャラクターたち
- 日本でも大人気!
- 「スヌーピーの日」に関するツイート集
チャールズ・M・シュルツ
チャールズ・M・シュルツは、アメリカの漫画家で、1950年からスヌーピーが登場する漫画「ピーナッツ」を書き始めています。その後、1986年に漫画家の殿堂入りを果たしました。
シュルツの生涯
シュルツは、1922年11月26日に貧しいドイツ系移民である理髪師の父、ノルウェー系移民の母の一人息子としてミネソタ州ミネアポリスにて生まれます。彼は、小さい頃から絵の才能に恵まれ、勉強も優秀で小学校時代に2学年飛び級しています。またこの頃、年上で体格も大きいクラスメイトに仲間はずれにされていた経験が、後の漫画「ピーナッツ」のチャーリー・ブラウンの誕生に繋がったといわれています。
名言+Quotesから引用
スヌーピーが登場する「ピーナッツ」
「ピーナッツ」は、1950年の連載から大人気で、50年に渡り描き続けられています。英語で『peanuts』は、「取るに足らない、つまらないもの」という意味です。実は、タイトルは、漫画の配信会社が勝手に決めたそうです。
タイトル『L’il Folks』、予定!?
作者自身がもともと考えていたタイトルは『L’il Folks』で、「小さな人々」という意味です。そのタイトルの通り、本作品にはスヌーピー以外、数々の個性がある子どもたちの登場があります。
個性豊かなキャラクターたち
不器用な「チャーリー・ブラウン」、飛ぶのが苦手な鳥の「ウッドストック」、安心毛布にしがみつく「ライナス」、怒りっぽい「ルーシー」。彼らの日常を中心に展開される短編ストーリーは、おもしろさや楽しさ以外、「人間の本質に迫る」ようなものや「人生の指針」になるものが描かれています。
日本でも大人気!
一方日本では、詩人の谷川氏などが翻訳を行い、「ピーナッツ」の魅力を伝えています。2016年4月には、六本木に期間限定で「スヌーピーミュージアム」が開館しました。そして、今でも人気のキャラクターグッズが販売されていて、コレクターがたくさんいます。正直、私も漫画そのものは観たことはないのですが、何故か子供の頃から知っていました。