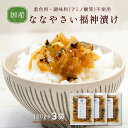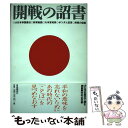「オシロイバナ」

基本情報
- 和名:オシロイバナ(白粉花)
- 学名:Mirabilis jalapa
- 英名:Four o’clock flower / Marvel of Peru
- 科名:オシロイバナ科
- 原産地:ペルーなど熱帯アメリカ
- 花期:夏(6月~10月)
- 草丈:50~100cmほど
- 分類:多年草(日本では一年草扱い)
オシロイバナについて

特徴
- 夕方に咲く花
昼間は閉じており、夕方から夜にかけて咲くのが特徴的です(名前の由来の一因にもなっています)。 - 豊富な花色と模様
赤、黄、白、ピンク、斑入りなど色のバリエーションが豊かで、同じ株に複数色の花が咲くこともあります。 - 芳香性がある
夕方になると、甘くほのかな香りを放ち、夜間に活動する蛾などを引き寄せます。 - 種に白粉のような粉
黒い種の中に白い粉状の胚乳が含まれており、これが和名「白粉花(おしろいばな)」の由来です。 - 丈夫で繁殖力が強い
日本では放っておいても種がこぼれて自然に増えるほどで、庭先や道端でもよく見かけます。
花言葉:「内気」

オシロイバナの花言葉のひとつに 「内気(Shyness)」 があります。
この言葉は、植物の性質や咲き方に深く関係しています。
● 夕暮れにだけ咲く「控えめな姿」
日中の明るい時間を避け、人目を避けるように夕方からひっそりと咲くことが、「内気」や「恥ずかしがり屋」のような性格を連想させます。まるで、人前に出ることをためらっているかのように、日没後にそっと花を開くその様子が、内気な心を象徴しているのです。
● 儚く静かな美しさ
咲いている時間も比較的短く、翌朝にはしぼんでしまうことが多いため、その儚く目立たない咲き方も、「自己主張しない性格」や「控えめな美しさ」の象徴とされました。
「夕暮れにだけ咲く」

陽が沈む少し前、古い町の裏通りにある小さな庭で、彼女はいつものように静かに水をやっていた。
この家には、誰も足を踏み入れない庭がある。表通りからは見えないその場所に、夕方になると花を咲かせる植物がいくつか育っていた。とりわけ一角に群れて咲くオシロイバナは、夕暮れの風にそっと揺れながら、その姿をほんのひとときだけ現す。
「咲いたのね」
少女――葉月(はづき)は、そっと膝をつき、咲き始めたばかりの花に視線を落とす。昼間にはまだ固く閉じていた蕾が、夕方の空気を感じ取って、ようやくゆるやかに開きはじめていた。

彼女は中学三年生。人と話すのが苦手で、クラスでもあまり目立たない存在だった。教室で手を挙げることも、誰かと一緒に昼食を食べることもない。ただ静かに時間を過ごし、下校後はこの庭に来るのが日課だった。
「夕方にしか咲かないなんて、なんだか、わたしみたいだよね」
ふと、そんな言葉がこぼれる。明るい時間に目立つ花はたくさんある。でもオシロイバナは違う。誰もが家に帰るころ、誰にも見られない時間帯に、ようやく花を開く。そして翌朝にはもうしぼんでしまう――そんな性質を持っている。
葉月はその花に、自分自身を重ねていた。

ある日、同じクラスの男子――新(あらた)が、彼女に声をかけてきた。
「この前、図書室で詩を読んでたよね。……好きなの?」
突然のことに、葉月は言葉を失った。誰かに話しかけられるなんて思ってもみなかった。小さくうなずいたあと、彼女は少しだけ微笑んだ。
新は、まるで夕焼けみたいな少年だった。明るくて、まっすぐで、でもどこか淡くて優しい。彼は葉月の「静けさ」に興味を持っていた。騒がしさの中にいない彼女が、まるで別の時間を生きているように見えたのだ。
それから、二人は少しずつ言葉を交わすようになった。放課後に図書室で本を読む日もあれば、時折、庭にも足を運ぶようになった。
「この花、オシロイバナっていうんだ」
ある夕方、葉月はそう言って、咲いたばかりの花を指さした。

「夕方だけ咲くんだ。朝になると、もう閉じちゃう。……なんだか恥ずかしがり屋みたいでしょ」
新は笑った。「でも、ちゃんと咲いてるんだね。誰かが気づいてくれるのを待ってるみたいに」
その言葉が、胸の奥にすっと染みこんだ。
――誰かが見つけてくれる。それだけで、咲く意味がある。
その夜、葉月はノートを開き、一行の詩を書いた。
「わたしは、夕暮れにだけ咲く けれど、あなたにだけは見てほしい」
オシロイバナの花言葉は「内気」。でもそれは、咲かないという意味じゃない。ただ、咲く時間が、ほんの少し静かなだけ。人知れず咲く花にも、やさしい想いと強さがある。
それを知っている人が、一人でもいるなら――きっと、それでいい。