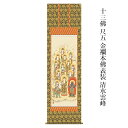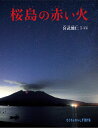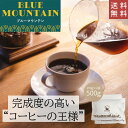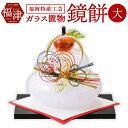「コデマリ」

コデマリ(小手毬)の花言葉には、「努力家」や「優雅」、「友情」などがあります。特に「努力家」という花言葉は、小さな白い花が丸く集まって咲く姿が、まるでひたむきに力を合わせて美しさを作り上げているように見えることに由来しています。
コデマリについて

科名:バラ科(Rosaceae)
原産地:日本や中国
特徴: 小さな花が球状に密集し、小さな手毬のような形になるのが特徴。春から初夏にかけて咲き、多年草として庭や公園などで人気のある植物です。
花言葉:努力家
「努力家」の花言葉は、コデマリのひとつひとつの小花が目立たなくても、集まることで大きな美しさを作り出していることに重なるものですね。努力を続ける人や、ひたむきに頑張る姿にぴったりのメッセージを伝える花です。
「小さな手毬の約束」

春の訪れを感じる頃、ある小さな村に住む少女リナは、一つの夢を抱いていた。それは、村の広場で春祭りの花飾りを作ることだった。村の人々が集まり、祝う春祭りは村の大切な行事。毎年、花飾りは村の名匠たちが作るため、リナにとっては遠い夢のように思えた。
リナは花が好きだったが、特に庭の隅に咲くコデマリが好きだった。小さな白い花が丸く集まり、控えめながらも凛とした美しさを放つその姿に、彼女は毎日話しかけていた。
「私もいつか、みんなに喜んでもらえる花を作れるかな?」

そんなある日、春祭りの準備で広場が賑わう中、リナは花飾りを作る仕事を手伝わせてほしいとお願いした。しかし、大人たちは首を横に振る。
「リナにはまだ無理だよ。花飾りは簡単じゃないんだ。」
傷つきながらも諦められなかったリナは、庭のコデマリにそっとつぶやいた。
「どうしたら、私も役に立てるのかな……。」

すると、その夜、不思議な夢を見た。夢の中でコデマリが語りかけてきたのだ。
「私たちは小さな花だけど、力を合わせて美しい形を作り出している。リナも自分の力を信じてごらん。」
目を覚ましたリナは、その言葉に勇気をもらい、村の人々が眠る間に一人で花飾りを作ることを決めた。庭からコデマリを摘み、他の花々と組み合わせて飾りを作る作業は大変だったが、彼女は夢中になった。

朝、広場にリナが作った花飾りが飾られているのを見て、村の人々は驚いた。小さな手毬のようなコデマリが中心に添えられたその飾りは、見たこともないほど優雅で温かみのあるものだった。
「リナが作ったのかい? 素晴らしいじゃないか!」
その言葉にリナは初めて笑顔を見せた。

春祭りの日、コデマリの花飾りは広場を美しく彩り、村の人々は皆、そのひたむきな努力を讃えた。それ以降、コデマリは村の「努力の花」として愛されるようになり、リナも村一番の花飾り職人として成長していった。
コデマリが教えてくれた「小さな力を合わせること」の大切さは、リナの心に深く刻まれ、その思いは花とともに村の春を彩り続けた。